【7月29日は福神漬の日】七福神に学ぶ“福を呼ぶ暮らし術”
「今日は何の日?」を日々のちょっとした楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。7月29日は福神漬の日。実はこれ、単なる漬物の話ではありません。福神漬に含まれる“7種の具材”が七福神に由来していること、ご存じでしたか?
忙しい現代の生活では、「福」や「運」といった抽象的なものに目を向ける機会が減っています。しかし、こうした“縁起を担ぐ暮らし”には、意外と実用的なヒントがたくさん詰まっているのです。
今回は「福神漬の日」にちなんで、“七福神に学ぶ福を呼び込む習慣”をご紹介します。日常の中にほんの少しの余白と、心のゆとりを取り戻してみませんか?
福神漬の日とは?|7月29日の由来と七福神の関係
福神漬とは、主にカレーライスの付け合わせとして親しまれている赤茶色の漬物。れんこん・大根・きゅうり・なす・なたまめ・しそ・生姜など、7種類の野菜が使われており、「七福神」にちなんで名付けられたといわれています。
7月29日は「七(しち)=7」「福(ふく)=ふ」「神(じん)=じん」と読める語呂合わせから「福神漬の日」とされています。
“ただの漬物”と侮るなかれ。この“福神”の発想、つまり「日常の中にちょっとした幸せや福を呼び込む」という考え方は、私たちの暮らしのヒントにもなります。
“福”が遠のく暮らし方とは?|現代人が見落としがちなこと
現代人は日々、仕事・家事・育児・情報の波に押し流されがちです。「やらなければならないこと」に追われ、「やりたいこと」「心が喜ぶこと」を後回しにしていないでしょうか?
特に30代〜50代のライフステージでは、子育てや親の介護、働き方の変化などさまざまな負荷がかかります。そんな中で、自分の心の声や小さな喜びに気づけなくなってしまう人も多いようです。
「朝の挨拶を省略する」「感謝の言葉を口にしない」「季節を感じる食事を意識しない」など、ほんの些細なことの積み重ねが、**“福が入りにくい暮らし”**をつくってしまっているのです。
七福神に学ぶ“福を招く”7つの習慣
ここで、七福神が象徴する“福の形”を生活に取り入れてみましょう。宗教的な意味ではなく、「日々の心がけ」として見てみると、思いがけないヒントが見つかります。
- 布袋尊(ほていそん)|笑顔と寛容の象徴
→ 忙しい朝でも笑顔で「おはよう」を。自分にも他人にも寛容でいよう。 - 恵比寿天(えびすてん)|仕事運・感謝の神
→ 今日の仕事に「ありがとう」を。やりがいや達成感を意識してみる。 - 毘沙門天(びしゃもんてん)|防衛と清浄の神
→ 部屋や持ち物を整えることが心を整える。片付けも“開運行動”。 - 弁財天(べんざいてん)|芸術・学び・表現の女神
→ 1日5分でいい、本を読む・日記を書く・新しい言葉に触れるなど。 - 大黒天(だいこくてん)|食の神・家庭円満
→ 食事を「ありがたく食べる」ことそのものが“福”への入り口。 - 寿老人(じゅろうじん)|健康・長寿の守り神
→ 毎日のウォーキングやストレッチで、“生きる土台”を整える。 - 福禄寿(ふくろくじゅ)|人間関係・徳の神
→ 「ありがとう」「助かるよ」「おかげさま」の一言で関係は変わる。
こうして見ると、どれも難しいことではありません。意識するだけで、今日から実践できる“福を招く行動”ばかりです。
まとめ|小さな“縁起”を取り入れることで暮らしは変わる
「運気を上げたい」「福を呼び込みたい」と願っても、いきなり大きな変化を求めると続きません。実は、“ちょっとした心がけ”が、毎日の質を変える第一歩なのです。
今日は「福神漬の日」。もし、冷蔵庫に入っているなら、今夜の食卓にちょこんと添えてみましょう。そして、七福神それぞれの“福”を思い浮かべながら、ひとつでも自分の習慣に取り入れてみてください。
心に余裕ができると、不思議と周囲の景色も変わってきます。忙しい毎日だからこそ、ほんの少しの“縁起担ぎ”を、暮らしのなかに。
今日も、あなたの1日に小さな“福”がありますように。

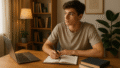
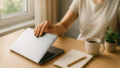
コメント