「シュワッチ!」の掛け声で空を舞い、光線技で怪獣を倒す正義のヒーロー「ウルトラマン」。子どもの頃に夢中になった人も多いのではないでしょうか。ですが、ウルトラマンには大人になった今だからこそ「へぇ~!」と驚くような雑学や裏話がたくさんあるんです。
今回は、そんなウルトラマンの“知ってるようで知らない”雑学を5つ、たっぷりご紹介します!
1. 実は「3分間しか戦えない」設定には大人の事情が?
ウルトラマンが地球上で戦える時間はわずか3分。これは、地球の大気が合わないからという設定になっていますが、実は制作サイドの都合が本当の理由だったんです。
1960年代のテレビ番組は、限られた時間と予算の中で作られていました。特撮シーンは時間もお金もかかるので、「3分」という制限を設けることで、戦闘シーンをコンパクトにまとめる工夫だったというわけです。
ちなみに、ウルトラマンの胸にある青い光「カラータイマー」は、活動限界を知らせるためのものですが、これも時間制限を視覚的に見せるために後から追加されたアイデア。苦肉の策が、逆にウルトラマンの個性になったというわけですね!
2. スペシウム光線のポーズは「空手」由来だった!?
ウルトラマンといえば、必殺技のスペシウム光線。両腕をL字に組んで放つあのポーズは、今やおなじみのアイコン的ポーズですよね。でも、あの構え方にはちょっとした秘密があります。
実はあのポーズ、**空手の型(かた)**や、当時流行していた東洋武術のイメージを元にしていると言われています。また、撮影当時のスーツアクター(中に入って演技する人)が「動きやすさ」と「見映えの良さ」を意識して作り上げたとも。
実際にやってみると分かりますが、あのL字ポーズって意外と体に負担がかからないんですよ。戦闘の途中でもすぐ構えられる実用的な必殺技ポーズなんです!
3. 初代ウルトラマンの名前、実は「ベムラー」だった?
初代ウルトラマンの企画段階では、実は現在のような「ヒーローの姿」ではありませんでした。当初は、「ベムラー」という名前の正義の怪獣が主人公になる予定だったんです。
ところが、視聴者に感情移入してもらいやすくするため、より人間に近い姿へとデザインが変更され、今のウルトラマンが誕生しました。ちなみに、その名残なのか、**第1話でウルトラマンが地球にやってきた理由が「ベムラーを追っていたから」**になっているのも面白いポイントです。
企画の名残が物語の骨組みに活かされてるのって、なんだか映画の裏話みたいで面白いですよね。
4. ウルトラマンの身長と体重、実は作品によってバラバラ?
「ウルトラマンってどれぐらい大きいの?」と聞かれたら、ファンなら「40メートル、3万5千トン」と答えたくなるかもしれません。でも実は、作品やシリーズによってサイズがけっこう違うんです。
たとえば、「ウルトラマンティガ」は身長53メートル、「ウルトラマンゼロ」は49メートルとやや大きめ。さらに、子ども時代のウルトラマンが登場したり、「変身後に巨大化するタイプ」もいたりと、設定はけっこう柔軟なんです。
ちなみに、初代ウルトラマンが登場した1960年代の東京タワーは333メートル。そこから逆算して、ちょうど見上げたときに「大きく見えるけど威圧感がない」サイズ感として、40メートル前後が選ばれたとも言われています。
5. 海外でも人気!ウルトラマンは世界進出していた
ウルトラマンは、日本国内だけでなく、アメリカ・ヨーロッパ・アジアなどでも放送されていました。特に1970年代にはアメリカで英語吹替版が放送され、「Ultraman」というタイトルでカルト的な人気を博したことも。
また、ハリウッドでもウルトラマンに注目が集まっており、2024年にはNetflixでCGアニメ映画『ウルトラマン:ライジング』が公開され話題になりました。
まさに、ウルトラマンは日本発のグローバルヒーロー。その活躍は今もなお世界中に広がっています。
 | バンダイ ウルトラアクションフィギュア ウルトラマン UAFウルトラマン [UAFウルトラマン] 価格:1780円 |
おわりに:大人だからこそ楽しめる「ウルトラマン」
子どもの頃に夢中で見ていたウルトラマン。でも、裏側や制作秘話を知ると、大人になった今だからこそ楽しめるポイントがたくさんあるんですね。
ウルトラマンは、世代を超えて語り継がれる“永遠のヒーロー”。これを機に、久しぶりに昔のウルトラシリーズを見返してみるのもいいかもしれません。懐かしさと新しい発見のダブルパンチで、きっとワクワクできるはずです。

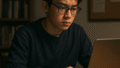

コメント